| 関係性 | いただいた金額 | お返し相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 友人・同僚 | 1-3万円 | 5,000-10,000円 | 半返し程度 |
| 親戚 | 3-10万円 | 10,000-30,000円 | 3分の1程度可 |
| 上司・目上の方 | 1-5万円 | 3,000-15,000円 | 3分の1程度 |
| 後輩・部下 | 1万円程度 | 5,000-10,000円 | 同額か少し上 |
お返しを贈るタイミングと方法
お返しのタイミングって、実は結構重要なんです。遅すぎても早すぎてもちょっと...という微妙なバランスがあるんですよね。私がプランナー時代に学んだポイントをお伝えしますね。

ベストなタイミングの判断基準
基本的には、お祝いをいただいてから1ヶ月以内がベストタイミング。でも、結婚式を挙げる場合は、式後1ヶ月以内でも大丈夫です。 私が担当したお客様で印象的だったのは、式の2ヶ月前にお祝いをいただいた新婦さん。「すぐにお返しした方がいいのかな」と悩んでいらっしゃいましたが、この場合は式後でOKなんです。ただし、お祝いをいただいたら、まずは電話やお手紙でお礼を伝えることは忘れずに。 入籍だけで式を挙げない場合は、入籍後1ヶ月以内を目安にしましょう。最近は多様な結婚スタイルがあるので、自分たちの状況に合わせて判断すれば大丈夫です。 うーん、でも正直なところ、1ヶ月って意外と短いんですよね。新婚旅行に行ったり、新生活の準備をしたりしていると、あっという間に過ぎちゃうんです。だから、お祝いをいただいたら早めに準備を始めることをおすすめします。
贈り方のマナーと注意点
お返しの贈り方にも、実はマナーがあるんです。一番丁寧なのは直接お渡しすること。でも現実的には、遠方の方や忙しい方には郵送することが多いですよね。 郵送の場合は、必ず事前にお電話やメールで「お返しをお送りします」という連絡を入れましょう。これ、意外と忘れがちなんですが、相手の方に「何か届く」ということを知らせておくのは大切なマナーです。 のしについても軽く触れておきますね。結婚内祝いの場合は、紅白の結び切りで「内祝」または「結婚内祝」と書きます。名前は新郎新婦の名前を連名で。旧姓で書くか新姓で書くかは、相手の方との関係性で判断してください。 そうそう、最近では配送の日時指定も大切なポイントです。相手の方のご都合を考えて、受け取りやすい日時を選ぶ心遣いも忘れずに。
喜ばれるギフトの選び方とカード型活用法
さて、ここからが本題というか、皆さんが一番悩まれるところかもしれませんね。「何を贈ったら喜んでもらえるの?」という質問、本当によく受けました。 正直に言うと、完璧な答えはないんです。でも、相手の方の立場や好みを考えて選べば、きっと喜んでいただけると思います。私の経験から言えることをお話ししますね。

ギフト選びの3つのポイント
ギフト選びで大切にしたいポイントは、以下の通りです: 消えものを選ぶ理由は、相手の方に負担をかけないため。
特に最近は、実用的なものが喜ばれる傾向にあります。私がサポートしたお客様で、高級なタオルセットを選ばれた方がいらっしゃったんですが、「毎日使えて嬉しい」ととても評判が良かったんです。 まあ、正直なところ、何を選んでも100%の正解はないんですけど...でも、相手のことを思って選んだものなら、その気持ちはきっと伝わりますよね。カード型ギフトのメリットと活用シーン
最近注目されているのが、カード型ギフトなんです。例えばKIZUNAなら、5,000円〜13,500円の価格設定でカード型の宅配ギフトサービスを提供しています。 カード型ギフトの良いところは、まず軽いこと。遠方の方への郵送でも送料を抑えられますし、相手の方も持ち帰りの負担がありません。それに、ゲストの方が自分で好きなものを選べるので、「これ、使わないかも...」という心配もないんです。
ただし、年配の方にはちょっと馴染みがないかもしれません。そういう場合は、事前に簡単に説明しておくか、従来型のギフトを選ぶ方が安心ですね。 引き出物でも最近はカード型が人気なので、詳しくは【結婚式引き出物に人気のカード型カタログギフト3品を徹底解説】も参考にしてみてください。時代の変化とともに、お返しの選択肢も広がっているんだなって感じます。 それにしても、カード型って本当に便利になりましたよね。私がプランナーを始めた頃にはなかった選択肢なので、時代の流れを感じます。でも、基本的な「相手を思いやる気持ち」は変わらないんですよね。よくある質問(FAQ)
-3.jpg)
高額なお祝いをいただいた場合のお返しは?
10万円や20万円といった高額なお祝いをいただいた場合、半返しだとかなりの負担になってしまいますよね。私の経験では、こういう場合は3分の1程度で十分です。 実際に、親戚から30万円のお祝いをいただいた新婦さんがいらっしゃったんですが、「15万円のお返しは正直厳しい」とおっしゃっていました。その時は10万円程度のお返しをされましたが、相手の方も「気持ちが伝わった」と喜んでくださったんです。 大切なのは金額よりも、感謝の気持ちをしっかりと伝えること。お返しと一緒に心のこもったお礼状を添えれば、きっと理解していただけると思います。
「お返しはいらない」と言われた時の対応は?
これ、本当によく聞かれる質問なんです。特に親しい友人や会社の上司から言われることが多いですよね。 基本的には、相手の言葉を素直に受け取って大丈夫です。ただし、お礼の気持ちは何らかの形で表現したいところ。例えば、新婚旅行のお土産を少し良いものにしたり、年賀状に写真を添えたり。 私が担当したお客様の中には、「お返しはいらない」と言ってくださった方に、後日手作りのお菓子を持参された方もいらっしゃいました。「これはお返しじゃなくて、お礼の気持ちです」と伝えたら、とても喜んでもらえたそうです。 形式にとらわれすぎず、相手との関係性を大切にすることが一番だと思います。
職場からの連名ギフトへのお返し方法は?
職場の皆さんからの連名でのお祝い、これもよくあるケースですね。基本的には、代表の方にまとめてお返しをするか、個別に小分けして配るかのどちらかです。 例えば、10人の連名で3万円をいただいた場合、一人当たり3,000円程度として、全体で10,000円程度のお返しを用意します。個包装されたお菓子やタオルなどを10個用意して、代表の方に「皆さんで分けてください」とお渡しするのが一般的です。 ただし、職場によっては「お返し禁止」というルールがある場合も。事前に確認しておくと安心ですね。私の経験では、お菓子のような消えものが一番喜ばれていました。
お返しが遅れてしまった場合の対応は?
生活が忙しくて、気づいたら2ヶ月、3ヶ月経ってしまった...なんてことも実際にはありますよね。でも大丈夫、今からでも間に合います。 遅れてしまった場合は、まずお詫びの気持ちを込めてお電話かお手紙でご連絡を。「お返しが遅れてしまい申し訳ございません」と素直にお詫びして、近日中にお返しをお送りする旨をお伝えしましょう。 そして、お返しと一緒にお詫びのお手紙を添えることが大切です。正直な気持ちを伝えれば、きっと理解していただけると思います。私が知っている限り、遅れたからといって関係が悪くなったという話は聞いたことがありません。 人間だもの、忘れることもありますよね。完璧を求めすぎず、気づいた時点で誠実に対応すれば大丈夫です。
結婚式をしない場合のお返しタイミングは?
最近は入籍のみで結婚式を挙げないカップルも増えていますよね。この場合のお返しタイミングについてもよく質問されます。 基本的には、入籍後1ヶ月以内を目安にお返しをします。結婚報告と同時期になることが多いので、報告のタイミングと合わせて計画を立てると良いですね。 私がサポートしたお客様の中には、入籍報告のお手紙と一緒にお返しをお送りした方もいらっしゃいました。「結婚式は挙げませんが、お祝いの気持ちに感謝しています」という言葉を添えて。 式を挙げない分、お返しでしっかりと感謝の気持ちを表現することが大切だと思います。形式は違っても、相手への思いやりは変わりませんからね。
地域によってお返しのルールは違うの?
これ、実は結構あるんです。地域によって、お返しの相場や品物に違いがある場合があります。 例えば、関西地方では「おため返し」という習慣があって、お祝いの半分程度をその場でお返しする地域もあります。また、東北地方では実用的なものよりも、お菓子などの消えものが好まれる傾向があったり。
出典:総務省統計局の家計調査年報
こちらをクリック!この記事のまとめ
結婚祝いのお返しについて、プランナー経験をもとにお話しさせていただきました。最後に、大切なポイントをもう一度整理しておきますね。 まず相場については、いただいた金額の半分から3分の1程度が基本。でも、高額なお祝いの場合は3分の1でも十分ですし、後輩など目下の方には同額程度でも構いません。大切なのは、相手の立場を考えて判断することです。 タイミングは、お祝いをいただいてから1ヶ月以内、または結婚式後1ヶ月以内を目安に。遅れてしまった場合も、誠実に対応すれば大丈夫です。 ギフト選びでは、相手の方が使いやすいものや消えものが基本。最近では、KIZUNAのようなカード型ギフトサービスも選択肢として人気が高まっています。カード1枚で済むので郵送しやすく、受け取る方も好きなものを選べるメリットがあります。 そして何より大切なのは、感謝の気持ちを込めること。完璧を求めすぎず、相手のことを思いやる心があれば、きっと喜んでいただけるお返しができると思います。 結婚という人生の大切な節目に、お祝いをいただけるということは本当にありがたいことです。そのお気持ちに、心を込めてお応えしていきたいですね。皆さんの新しい人生が、多くの方々の祝福に包まれて素晴らしいものになりますように。
 )
[_post_items_0_post_items_editor_text] => Array
(
[0] => field_5f32345e39f0f
)
[post_items] => Array
(
[0] => a:1:{i:0;s:17:"post_items_editor";}
)
[_post_items] => Array
(
[0] => field_5f3233ec39f0e
)
[_oembed_29ce7e2f9d31414afcdea08046d7f80c] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_thumbnail_id] => Array
(
[0] => 4440
)
[views] => Array
(
[0] => 461
)
[_wp_old_date] => Array
(
[0] => 2025-08-10
[1] => 2025-11-25
)
[show_auto_toc] => Array
(
[0] => 0
)
[_show_auto_toc] => Array
(
[0] => field_68dcc41d1e9b8
)
)
)
[_post_items_0_post_items_editor_text] => Array
(
[0] => field_5f32345e39f0f
)
[post_items] => Array
(
[0] => a:1:{i:0;s:17:"post_items_editor";}
)
[_post_items] => Array
(
[0] => field_5f3233ec39f0e
)
[_oembed_29ce7e2f9d31414afcdea08046d7f80c] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_thumbnail_id] => Array
(
[0] => 4440
)
[views] => Array
(
[0] => 461
)
[_wp_old_date] => Array
(
[0] => 2025-08-10
[1] => 2025-11-25
)
[show_auto_toc] => Array
(
[0] => 0
)
[_show_auto_toc] => Array
(
[0] => field_68dcc41d1e9b8
)
)
結婚祝いをいただいた時の「お返しってどうすればいいの?」という悩み、私もプランナー時代に本当によく相談を受けました。金額はどれくらい?いつまでに贈ればいい?何を選んだら喜んでもらえる?
そういえば、つい先月も30代の新婦さんから「親戚から10万円もいただいちゃって…」と困った様子で相談されたんですが、最初はみんなそんな感じなんですよね。でも大丈夫、基本さえ押さえれば決して難しいものじゃありません。
私が式場で300組以上のお客様をサポートした経験をもとに、2025年現在のマナーも含めて、結婚祝いのお返しについて分かりやすくお伝えしていきますね。最近では従来の品物だけでなく、カード型ギフトなど新しい選択肢も増えているので、それらの活用法も含めてご紹介します。
・贈るタイミングはお祝い受領後またはお式後1ヶ月以内
・ギフト選びは消えものや実用品、カード型も人気の選択肢
・感謝の気持ちを込めた心遣いが何より大切
- 1. 結婚祝いのお返しの基本ルールと相場感
- ➤ お返しが必要なケースと不要なケース
- ➤ 関係性別の相場一覧表
- 2. お返しを贈るタイミングと方法
- ➤ ベストなタイミングの判断基準
- ➤ 贈り方のマナーと注意点
- 3. 喜ばれるギフトの選び方とカード型活用法
- ➤ ギフト選びの3つのポイント
- ➤ カード型ギフトのメリットと活用シーン
- 4. よくある質問(FAQ)
- ➤ 高額なお祝いをいただいた場合のお返しは?
- ➤ 「お返しはいらない」と言われた時の対応は?
- ➤ 職場からの連名ギフトへのお返し方法は?
- ➤ お返しが遅れてしまった場合の対応は?
- ➤ 結婚式をしない場合のお返しタイミングは?
- ➤ 地域によってお返しのルールは違うの?
- 5. この記事のまとめ
結婚祝いのお返しの基本ルールと相場感
結婚祝いのお返し、正式には「結婚内祝い」と呼ばれるものですが、これって実は日本独特の美しい文化なんです。いただいた幸せを、お返しという形で分かち合うという考え方。私がプランナーをしていた頃、海外のお客様によく「なんて素敵な習慣なの」と言われました。
でも、美しい文化だからこそ、きちんとしたマナーがあるんですよね。基本的なルールを知っておけば、相手の方にも喜んでいただけるお返しができるんです。
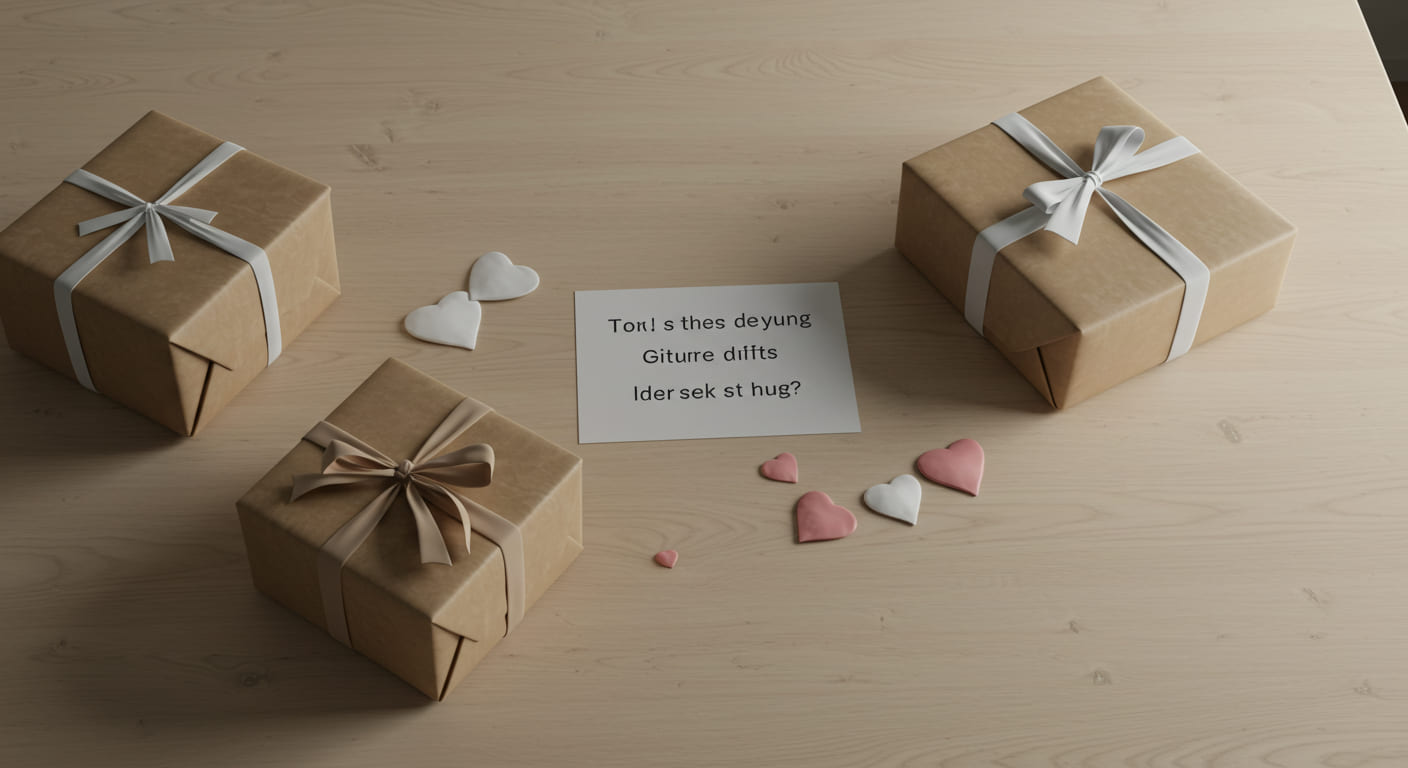
お返しが必要なケースと不要なケース
まず最初に、お返しが必要かどうかの判断について。これ、意外と迷う方が多いんです。
お返しが必要なのは、基本的に結婚式に参列されなかった方からお祝いをいただいた場合。結婚式に来てくださった方には、引き出物や料理でおもてなしをしているので、基本的にはそれがお返しという考え方なんです。
ただし、結婚式に参列された方でも、ご祝儀以外に別途お祝いをいただいた場合は、やっぱりお返しをするのがマナーです。私の経験では、親戚の方が式当日に現金以外にも品物をくださったり、会社の上司が個人的にお祝いを送ってくださったりというケースがよくありました。
逆に、お返し不要のケースもあります。両親や祖父母など、家族からのお祝いには基本的にお返しは不要。「お返しはいらない」とはっきり言われた場合も、無理に品物を贈る必要はありませんが、お礼の気持ちは別の形で表現したいですね。
関係性別の相場一覧表
お返しの相場、これが一番気になるところですよね。
出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2024
によると、いただいた金額の半分から3分の1程度が一般的とされています。
| 関係性 | いただいた金額 | お返し相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 友人・同僚 | 1-3万円 | 5,000-10,000円 | 半返し程度 |
| 親戚 | 3-10万円 | 10,000-30,000円 | 3分の1程度可 |
| 上司・目上の方 | 1-5万円 | 3,000-15,000円 | 3分の1程度 |
| 後輩・部下 | 1万円程度 | 5,000-10,000円 | 同額か少し上 |
実際のところ、金額よりも気持ちが大切なんです。私がサポートしたお客様の中には、「計算通りじゃなくても、相手の方が喜んでくださる物を選びたい」とおっしゃる方も多くいらっしゃいました。そういう心遣いって、きっと伝わると思うんです。
そういえば、最近では「お返しの負担を軽くしたい」という声も増えています。特に高額なお祝いをいただいた場合、従来の半返しだとかなりの負担になってしまいますからね。そんな時は、3分の1程度でも十分マナーに適っているので、無理をしすぎないことも大切だと思います。
お返しを贈るタイミングと方法
お返しのタイミングって、実は結構重要なんです。遅すぎても早すぎてもちょっと…という微妙なバランスがあるんですよね。私がプランナー時代に学んだポイントをお伝えしますね。

ベストなタイミングの判断基準
基本的には、お祝いをいただいてから1ヶ月以内がベストタイミング。でも、結婚式を挙げる場合は、式後1ヶ月以内でも大丈夫です。
私が担当したお客様で印象的だったのは、式の2ヶ月前にお祝いをいただいた新婦さん。「すぐにお返しした方がいいのかな」と悩んでいらっしゃいましたが、この場合は式後でOKなんです。ただし、お祝いをいただいたら、まずは電話やお手紙でお礼を伝えることは忘れずに。
入籍だけで式を挙げない場合は、入籍後1ヶ月以内を目安にしましょう。最近は多様な結婚スタイルがあるので、自分たちの状況に合わせて判断すれば大丈夫です。
うーん、でも正直なところ、1ヶ月って意外と短いんですよね。新婚旅行に行ったり、新生活の準備をしたりしていると、あっという間に過ぎちゃうんです。だから、お祝いをいただいたら早めに準備を始めることをおすすめします。
贈り方のマナーと注意点
お返しの贈り方にも、実はマナーがあるんです。一番丁寧なのは直接お渡しすること。でも現実的には、遠方の方や忙しい方には郵送することが多いですよね。
郵送の場合は、必ず事前にお電話やメールで「お返しをお送りします」という連絡を入れましょう。これ、意外と忘れがちなんですが、相手の方に「何か届く」ということを知らせておくのは大切なマナーです。
のしについても軽く触れておきますね。結婚内祝いの場合は、紅白の結び切りで「内祝」または「結婚内祝」と書きます。名前は新郎新婦の名前を連名で。旧姓で書くか新姓で書くかは、相手の方との関係性で判断してください。
そうそう、最近では配送の日時指定も大切なポイントです。相手の方のご都合を考えて、受け取りやすい日時を選ぶ心遣いも忘れずに。
喜ばれるギフトの選び方とカード型活用法
さて、ここからが本題というか、皆さんが一番悩まれるところかもしれませんね。「何を贈ったら喜んでもらえるの?」という質問、本当によく受けました。
正直に言うと、完璧な答えはないんです。でも、相手の方の立場や好みを考えて選べば、きっと喜んでいただけると思います。私の経験から言えることをお話ししますね。

ギフト選びの3つのポイント
ギフト選びで大切にしたいポイントは、以下の通りです:
消えものを選ぶ理由は、相手の方に負担をかけないため。
特に最近は、実用的なものが喜ばれる傾向にあります。私がサポートしたお客様で、高級なタオルセットを選ばれた方がいらっしゃったんですが、「毎日使えて嬉しい」ととても評判が良かったんです。
まあ、正直なところ、何を選んでも100%の正解はないんですけど…でも、相手のことを思って選んだものなら、その気持ちはきっと伝わりますよね。
カード型ギフトのメリットと活用シーン
最近注目されているのが、カード型ギフトなんです。例えばKIZUNAなら、5,000円〜13,500円の価格設定でカード型の宅配ギフトサービスを提供しています。
カード型ギフトの良いところは、まず軽いこと。遠方の方への郵送でも送料を抑えられますし、相手の方も持ち帰りの負担がありません。それに、ゲストの方が自分で好きなものを選べるので、「これ、使わないかも…」という心配もないんです。
ただし、年配の方にはちょっと馴染みがないかもしれません。そういう場合は、事前に簡単に説明しておくか、従来型のギフトを選ぶ方が安心ですね。
引き出物でも最近はカード型が人気なので、詳しくは【結婚式引き出物に人気のカード型カタログギフト3品を徹底解説】も参考にしてみてください。時代の変化とともに、お返しの選択肢も広がっているんだなって感じます。
それにしても、カード型って本当に便利になりましたよね。私がプランナーを始めた頃にはなかった選択肢なので、時代の流れを感じます。でも、基本的な「相手を思いやる気持ち」は変わらないんですよね。
よくある質問(FAQ)
-3.jpg)
高額なお祝いをいただいた場合のお返しは?
10万円や20万円といった高額なお祝いをいただいた場合、半返しだとかなりの負担になってしまいますよね。私の経験では、こういう場合は3分の1程度で十分です。
実際に、親戚から30万円のお祝いをいただいた新婦さんがいらっしゃったんですが、「15万円のお返しは正直厳しい」とおっしゃっていました。その時は10万円程度のお返しをされましたが、相手の方も「気持ちが伝わった」と喜んでくださったんです。
大切なのは金額よりも、感謝の気持ちをしっかりと伝えること。お返しと一緒に心のこもったお礼状を添えれば、きっと理解していただけると思います。
「お返しはいらない」と言われた時の対応は?
これ、本当によく聞かれる質問なんです。特に親しい友人や会社の上司から言われることが多いですよね。
基本的には、相手の言葉を素直に受け取って大丈夫です。ただし、お礼の気持ちは何らかの形で表現したいところ。例えば、新婚旅行のお土産を少し良いものにしたり、年賀状に写真を添えたり。
私が担当したお客様の中には、「お返しはいらない」と言ってくださった方に、後日手作りのお菓子を持参された方もいらっしゃいました。「これはお返しじゃなくて、お礼の気持ちです」と伝えたら、とても喜んでもらえたそうです。
形式にとらわれすぎず、相手との関係性を大切にすることが一番だと思います。
職場からの連名ギフトへのお返し方法は?
職場の皆さんからの連名でのお祝い、これもよくあるケースですね。基本的には、代表の方にまとめてお返しをするか、個別に小分けして配るかのどちらかです。
例えば、10人の連名で3万円をいただいた場合、一人当たり3,000円程度として、全体で10,000円程度のお返しを用意します。個包装されたお菓子やタオルなどを10個用意して、代表の方に「皆さんで分けてください」とお渡しするのが一般的です。
ただし、職場によっては「お返し禁止」というルールがある場合も。事前に確認しておくと安心ですね。私の経験では、お菓子のような消えものが一番喜ばれていました。
お返しが遅れてしまった場合の対応は?
生活が忙しくて、気づいたら2ヶ月、3ヶ月経ってしまった…なんてことも実際にはありますよね。でも大丈夫、今からでも間に合います。
遅れてしまった場合は、まずお詫びの気持ちを込めてお電話かお手紙でご連絡を。「お返しが遅れてしまい申し訳ございません」と素直にお詫びして、近日中にお返しをお送りする旨をお伝えしましょう。
そして、お返しと一緒にお詫びのお手紙を添えることが大切です。正直な気持ちを伝えれば、きっと理解していただけると思います。私が知っている限り、遅れたからといって関係が悪くなったという話は聞いたことがありません。
人間だもの、忘れることもありますよね。完璧を求めすぎず、気づいた時点で誠実に対応すれば大丈夫です。
結婚式をしない場合のお返しタイミングは?
最近は入籍のみで結婚式を挙げないカップルも増えていますよね。この場合のお返しタイミングについてもよく質問されます。
基本的には、入籍後1ヶ月以内を目安にお返しをします。結婚報告と同時期になることが多いので、報告のタイミングと合わせて計画を立てると良いですね。
私がサポートしたお客様の中には、入籍報告のお手紙と一緒にお返しをお送りした方もいらっしゃいました。「結婚式は挙げませんが、お祝いの気持ちに感謝しています」という言葉を添えて。
式を挙げない分、お返しでしっかりと感謝の気持ちを表現することが大切だと思います。形式は違っても、相手への思いやりは変わりませんからね。
地域によってお返しのルールは違うの?
これ、実は結構あるんです。地域によって、お返しの相場や品物に違いがある場合があります。
例えば、関西地方では「おため返し」という習慣があって、お祝いの半分程度をその場でお返しする地域もあります。また、東北地方では実用的なものよりも、お菓子などの消えものが好まれる傾向があったり。
出典:総務省統計局の家計調査年報
を見ても、地域によってギフトに関する支出に差があることがわかります。
でも、あまり神経質になりすぎる必要はありません。基本的なマナーさえ押さえておけば、地域差があってもそれほど大きな問題にはならないと思います。心配な場合は、地元の年配の方や親戚に相談してみるのも良いですね。
この記事のまとめ
結婚祝いのお返しについて、プランナー経験をもとにお話しさせていただきました。最後に、大切なポイントをもう一度整理しておきますね。
まず相場については、いただいた金額の半分から3分の1程度が基本。でも、高額なお祝いの場合は3分の1でも十分ですし、後輩など目下の方には同額程度でも構いません。大切なのは、相手の立場を考えて判断することです。
タイミングは、お祝いをいただいてから1ヶ月以内、または結婚式後1ヶ月以内を目安に。遅れてしまった場合も、誠実に対応すれば大丈夫です。
ギフト選びでは、相手の方が使いやすいものや消えものが基本。最近では、KIZUNAのようなカード型ギフトサービスも選択肢として人気が高まっています。カード1枚で済むので郵送しやすく、受け取る方も好きなものを選べるメリットがあります。
そして何より大切なのは、感謝の気持ちを込めること。完璧を求めすぎず、相手のことを思いやる心があれば、きっと喜んでいただけるお返しができると思います。
結婚という人生の大切な節目に、お祝いをいただけるということは本当にありがたいことです。そのお気持ちに、心を込めてお応えしていきたいですね。皆さんの新しい人生が、多くの方々の祝福に包まれて素晴らしいものになりますように。





