| 関係性 | いただく金額の目安 | 内祝いの相場 | 選ぶ商品の特徴 |
|---|---|---|---|
| 両親・兄弟姉妹 | 5万円〜10万円 | 3分の1程度 | 甘えても良い関係 |
| 親戚・親族 | 3万円〜5万円 | 半額程度 | 格式を重視 |
| 職場上司 | 1万円〜3万円 | 半額程度 | 今後の関係も考慮 |
| 友人・同僚 | 1万円〜3万円 | 半額程度 | 実用性重視 |
| 職場一同 | 5千円〜1万円 | 半額程度 | みんなで分けられるもの |
出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2024
こちらをクリック!のしと表書きの正しいマナー
のしの書き方って、正直言うと私も最初は全然わからなくて困りました。「結び切り?蝶結び?」「表書きは何て書くの?」「名前は旧姓?新姓?」...疑問だらけで、確か母に電話で聞きながら準備した記憶があります。 でも一度覚えてしまえば、そんなに難しくないんです。のしは相手への敬意を表す大切な要素なので、基本的なルールは押さえておきたいところですね。特に年配の方は、のしがきちんとしているかどうかをよく見ていらっしゃるので、失礼のないようにしたいものです。 そういえば、この前友人が「のしって自分で書くの?お店でやってもらうの?」って聞いてきたんですが、最近はお店で丁寧に書いてもらえるところが多いので、そんなに心配しなくても大丈夫なんですよね。

のしの基本ルールと選び方
のしで一番重要なのは「水引」の選び方です。結婚内祝いでは、必ず「結び切り」を使います。これは「一度きりの慶事」という意味で、結婚は何度も繰り返すものではないからです。間違っても「蝶結び」は使わないでくださいね。私も最初、デパートで「どちらにしますか?」って聞かれて迷ったんですが、店員さんが教えてくれました。 水引の色は、紅白または金銀が一般的です。紅白の方が一般的で、金銀は特に格式を重視したい場合に使います。本数は5本か10本ですが、結婚関連では10本が正式とされています。まあ、最近はあまり細かく気にする人も少なくなってきているようですが、基本は知っておいた方が安心ですよね。 のしの大きさも、贈り物の大きさに合わせて選びます。小さな品物に大きなのしをつけるとバランスが悪いですし、逆も然りです。お店の方に相談すれば、適切なサイズを選んでくれますよ。
表書きの書き方と注意点
表書きは「内祝」または「結婚内祝」と書くのが一般的です。私は「内祝」にしましたが、どちらでも問題ありません。「寿」と書く場合もありますが、これは結婚式の引き出物などでよく使われるので、内祝いでは「内祝」の方が適切だと思います。 下段には贈り主の名前を書きますが、ここが一番悩むところかもしれません。結婚後なら新しい姓で、夫婦連名で書くのが基本です。「田中太郎・花子」のように、右側に夫の名前、左側に妻の名前を書きます。 ただし、職場関係で旧姓の方が通りが良い場合は、カッコ内に旧姓を併記することもあります。例えば「田中花子(旧姓:佐藤)」のような感じですね。うろ覚えなんですが、確か地域によっては両家の姓を併記するところもあったような気がします。詳しくは覚えてないんですが、その辺りは地域の慣習に合わせるのが良いでしょう。 大切なのは、相手が「誰からのお返し」なのかすぐにわかることです。特に親戚関係では、姓が変わったことを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、そういった配慮も必要ですね。 KIZUNAのようなカード型ギフトサービスでも、のしのデザインはちゃんと用意されていて、名前の印字も対応してもらえます。最近はこういったサービスを利用する方も増えているので、準備の手間を省きたい場合は検討してみても良いかもしれません。
よくある質問(FAQ)
-2.jpg)
内祝いはいつまでに贈ればいい?
これは本当によく聞かれる質問です。基本的には、お祝いをいただいてから1ヶ月以内に贈るのがマナーとされています。私の場合は、お祝いをいただいた日をメモしておいて、遅くても3週間以内には発送するようにしていました。 ただし、結婚式を挙げる場合は、式後1ヶ月以内でも大丈夫です。式の準備で忙しいのは皆さんわかってくださいますからね。万が一遅れてしまった場合は、お詫びの一言を添えることが大切です。私の友人も、新婚旅行から帰ってきてから慌てて準備していましたが、丁寧なお礼状と一緒に贈ったら、皆さん快く受け取ってくださったそうです。
連名でお祝いをもらった場合は?
夫婦連名でお祝いをいただいた場合は、基本的に1つの内祝いで大丈夫です。ただし、のしには「○○様・○○様」と連名でいただいた通りに、こちらも連名でお返しするのがマナーです。 私が悩んだのは、友人カップルから連名でお祝いをいただいた時でした。まだ結婚前のカップルだったので、それぞれ個別にお返しした方がいいのか迷ったんです。結局、1つの内祝いにして、二人の名前を併記した形でお贈りしたら、とても喜んでもらえました。
商品券やギフトをもらった時の対応は?
金額がわからない商品券やギフトをいただいた時って、本当に困りますよね。私も実際に経験があります。そういう時は、同じブランドのオンラインショップで似たような商品の価格を調べてみるのが一つの方法です。 どうしてもわからない場合は、3,000円、5,000円、10,000円のどの価格帯に近いかを推測して、その半額程度で内祝いを準備します。迷った時は、少し多めに見積もった方が安全だと思います。私の経験では、心配しすぎるより、感謝の気持ちがしっかり伝わることの方が大切です。
職場の皆さんからお祝いをもらった場合は?
職場一同からお祝いをいただいた場合は、みんなで分けられるお菓子や食べ物でお礼するのが一般的です。個包装のものを人数分より少し多めに用意して、「心ばかりの品ですが」というメッセージを添えます。 私の場合は、20人程度の部署から3万円のお祝いをいただいたので、1万5千円程度の詰め合わせお菓子を選びました。のしには「御礼」と書いて、自分たちの名前を入れます。後日、「美味しかったです」という声をたくさんいただけて、本当に嬉しかったです。
結婚式を挙げない場合でも内祝いは必要?
はい、式を挙げない場合でもお祝いをいただいたら内祝いは必要です。むしろ、式がない分、お祝いをくださった方への感謝をより丁寧に表現したいものですよね。 入籍の報告をした日を起点に考えて、1ヶ月以内を目安に準備すれば良いでしょう。お礼状には「ささやかながら内祝いをお贈りします」という一文を添えると、気持ちが伝わりやすくなります。
お礼状は手書きでないとダメ?
手書きの方が気持ちは伝わりやすいですが、印刷でも全然問題ありません。大切なのは、感謝の気持ちがきちんと込められているかどうかです。私の場合は、印刷した文章の最後に手書きで一言添えるようにしていました。
この記事のまとめ
結婚内祝いについて、基本的な意味から具体的な選び方、金額設定、のしのマナーまで詳しくお話ししてきました。私自身の体験を振り返ってみると、最初は本当にわからないことだらけで不安でしたが、一つひとつ丁寧に準備していけば、きっと感謝の気持ちは相手に伝わるものだと感じています。 まず、結婚内祝いは単なる「お返し」ではなく、喜びを分かち合うという本来の意味があることを理解できました。現代では感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとしての役割が重要で、相手との関係をより良好に保つための大切な習慣なんですね。 選び方については、相手との関係性を最優先に考えることが成功の秘訣です。年齢層や親密度、ライフスタイルを考慮して、消えものか長く使えるものを中心に選べば失敗は少ないでしょう。最近人気のカタログギフトやカード型サービスなら、相手が自分で選べるので安心です。 金額設定では「半返し」が基本原則ですが、関係性によって柔軟に調整することが大切です。身内には3分の1程度、職場関係や親戚にはしっかり半額程度を目安にしつつ、何より相手のことを思って選ぶ気持ちが重要です。 のしについては、結び切りの水引を使い、表書きは「内祝」、名前は夫婦連名で書くのが基本ルール。細かいマナーも大切ですが、相手への敬意を表すという心構えがあれば大丈夫です。 私が一番お伝えしたいのは、完璧を求めすぎなくても良いということです。形式やマナーも大切ですが、それ以上に「お祝いをくださった方への感謝の気持ちを伝えたい」という思いがあれば、きっと相手にも伝わります。結婚という人生の節目に、大切な方々との関係を深めるきっかけとして、心を込めて内祝いを準備していただければと思います。
 )
[_post_items_0_post_items_editor_text] => Array
(
[0] => field_5f32345e39f0f
)
[views] => Array
(
[0] => 657
)
[_wp_old_date] => Array
(
[0] => 2024-12-05
[1] => 2025-07-11
)
[_thumbnail_id] => Array
(
[0] => 3971
)
[show_auto_toc] => Array
(
[0] => 0
)
[_show_auto_toc] => Array
(
[0] => field_68dcc41d1e9b8
)
)
)
[_post_items_0_post_items_editor_text] => Array
(
[0] => field_5f32345e39f0f
)
[views] => Array
(
[0] => 657
)
[_wp_old_date] => Array
(
[0] => 2024-12-05
[1] => 2025-07-11
)
[_thumbnail_id] => Array
(
[0] => 3971
)
[show_auto_toc] => Array
(
[0] => 0
)
[_show_auto_toc] => Array
(
[0] => field_68dcc41d1e9b8
)
)
結婚内祝いって、最初はなんのことかよくわからなくて、私も結婚が決まった時に「内祝いって何?お返し?」って混乱した記憶があります。お祝いをいただいた時の感謝の気持ちを形にして伝える大切な習慣なんですが、いざ準備しようと思うと「いつまでに?」「いくらぐらい?」「のしはどう書くの?」と疑問がどんどん湧いてきますよね。
私自身、入籍した時に親戚や友人、職場の方々からお祝いをいただいて、本当にありがたい気持ちでいっぱいになったんです。でも同時に「お返ししなきゃ」という気持ちと「何をどうすればいいの?」という不安が入り混じって…。そういえば、確か母に相談した時も「昔と今では少し違うから」って言われて、余計に混乱したんですよね。
最近では結婚のスタイルも多様化していて、式を挙げないカップルも増えています。
出典:厚生労働省の人口動態統計
によると、結婚に関する価値観や慣習も変化しており、内祝いのマナーについても時代に合わせた柔軟な対応が求められています。
この記事では、結婚内祝いの基本的な意味から、実際の選び方、適切な金額設定、のしの書き方まで、私の体験も交えながら詳しくお話ししていきます。「こんな時はどうすればいいの?」という疑問にもお答えしますので、安心して準備を進めていただけると思います。
・選び方は相手との関係性を最優先に考え、年齢層やライフスタイルに合わせて消えものか実用品を選ぶ
・金額は「半返し」が基本だが身内は3分の1、職場関係は半額程度と関係性で柔軟に調整する
・のしは結び切りの水引で「内祝」と表書きし、夫婦連名で記載するのがマナーの基本
- 1. 結婚内祝いの基本的な意味と目的を理解する
- ➤ 内祝いと「お返し」の違いとは
- ➤ 現代における結婚内祝いの役割
- 2. 結婚内祝いの選び方で押さえるべきポイント
- ➤ 相手との関係性を考慮した選び方
- ➤ 喜ばれる内祝いギフトの特徴
- 3. 金額設定の基本ルールと相場感
- ➤ 半返しの原則と例外ケース
- ➤ 関係性別の相場目安
- 4. のしと表書きの正しいマナー
- ➤ のしの基本ルールと選び方
- ➤ 表書きの書き方と注意点
- 5. よくある質問(FAQ)
- ➤ 内祝いはいつまでに贈ればいい?
- ➤ 連名でお祝いをもらった場合は?
- ➤ 商品券やギフトをもらった時の対応は?
- ➤ 職場の皆さんからお祝いをもらった場合は?
- ➤ 結婚式を挙げない場合でも内祝いは必要?
- ➤ お礼状は手書きでないとダメ?
- 6. この記事のまとめ
結婚内祝いの基本的な意味と目的を理解する
結婚内祝いについて調べ始めると、まず「内祝い」という言葉の意味でつまずく方も多いんじゃないでしょうか。私も最初は「内祝いって内輪のお祝い?」なんて勘違いしていました。実は、この「内祝い」には深い意味があって、単なるお返しとは少し違うんです。
正しく理解しておくことで、贈る時の気持ちも変わってきますし、相手にも真心が伝わりやすくなります。現代では形式にとらわれすぎる必要はありませんが、基本的な意味を知っておくと、いざという時に自信を持って対応できるんですよね。

内祝いと「お返し」の違いとは
「内祝い」と「お返し」、この違いって意外と知られていないんです。私も結婚するまで、この二つを同じ意味で使っていました。でも、本来の内祝いは「身内の慶事を近しい人と分かち合う」という意味だったんです。つまり、お祝いをもらったからお返しするのではなく、こちらの喜びをおすそ分けするという考え方。
確か親戚の伯母に教えてもらったんですが、昔は結婚した家が「うちに良いことがあったので、皆さんにもこの喜びを」という気持ちで品物を配っていたんだそうです。現代では、お祝いをいただいた方への感謝の気持ちを込めた「お返し」という意味合いが強くなっていますが、根底にある「喜びを分かち合う」という精神は変わらないんですよね。
この違いを理解していると、内祝いを選ぶ時の気持ちも変わってきます。「義務だから仕方なく」ではなく、「嬉しさを一緒に感じてもらいたい」という温かい気持ちで準備できるんです。
現代における結婚内祝いの役割
現代の結婚内祝いは、感謝の気持ちを伝える大切なコミュニケーションツールとしての役割が強くなっています。私の周りでも、内祝いを通じて「ちゃんとした人だな」という印象を持ってもらえたという話をよく聞きます。
特に最近は、職場関係や友人との付き合い方も多様化していて、お祝いをいただく場面も様々です。連名でいただいたり、職場一同からいただいたり、金額がわからないギフトをいただいたり…。そんな時に、相手の気持ちに寄り添った適切な内祝いをお贈りできれば、今後の関係もより良好に保てるんです。
それに、内祝いって相手だけでなく、贈る側にとっても「お世話になった方への感謝を形にできた」という満足感が得られるんですよね。私も実際に内祝いをお贈りした後、「ありがとうございました」というお返事をいただいた時は、本当に嬉しかったです。
結婚内祝いの選び方で押さえるべきポイント
結婚内祝いを選ぶ時って、本当に迷いますよね。私も当時、デパートの内祝いコーナーで1時間以上悩んでいた記憶があります。「これで喜んでもらえるかな?」「失礼にならないかな?」って考えれば考えるほど、わからなくなってしまって…。
でも実際のところ、内祝い選びにはちゃんとしたコツがあるんです。相手のことを思いながら選べば、きっと気持ちは伝わります。私がプランナー時代に見てきた成功例や、自分の体験を踏まえて、押さえておきたいポイントをお話ししますね。
そういえば、この前友人から「内祝い選びのコツってある?」って相談されたんですが、やっぱり多くの人が同じところで悩んでいるんだなと感じました。形式的なルールも大切ですが、相手の立場に立って考えることが一番重要なんです。

相手との関係性を考慮した選び方
内祝い選びで一番大切なのは、贈る相手との関係性をしっかり考えることです。私も最初は「みんな同じものでいいかな」なんて思っていたんですが、実際にお祝いをくださった方の顔を思い浮かべてみると、それぞれ全然違うんですよね。
例えば、親しい友人なら少しカジュアルで実用的なものでも喜んでもらえますが、職場の上司や年配の親族には、もう少しフォーマルで格式のあるものが適しています。私の場合、20代の友人にはおしゃれな雑貨やグルメギフト、60代の伯母には上品な和菓子セットを選んだりしました。
こうして整理してみると、それぞれに適した内祝いのイメージが湧いてきませんか?
喜ばれる内祝いギフトの特徴
「どんなものが喜ばれるの?」これは本当によく聞かれる質問です。私の経験から言うと、喜ばれる内祝いにはいくつかの共通点があります。
まず、「消えものか、長く使えるもの」のどちらかがおすすめです。消えものというのは、お菓子や食品など使い切れるもの。これなら好みに合わなくても負担になりませんし、家族みんなで楽しんでもらえます。一方、長く使えるものなら、上質なタオルや食器など、日常的に使ってもらえるものがいいですね。
そして最近人気なのが、相手が自分で選べるカタログギフトです。KIZUNAのようなカード型のギフトサービスなら、受け取った方が好きなタイミングで、好みに合った商品を選べるので、失敗が少ないんです。しかも荷物にならないので、特に遠方の方には喜ばれています。
私が実際に贈って好評だったのは、地元の有名な和菓子店のお菓子セットや、今治タオルのような定番ブランドの実用品でした。やっぱり「聞いたことがある」「使いやすい」というのは大きなポイントなんだなと感じています。
—
金額設定の基本ルールと相場感
内祝いの金額設定って、本当に悩ましいですよね。私も最初は「いくらぐらいが適正なの?」って夜中までインターネットで調べていました。高すぎても相手に気を遣わせてしまうし、安すぎても失礼になってしまう…。この絶妙なバランスを見つけるのが難しいんです。
基本的には「半返し」という考え方があるんですが、最近はもう少し柔軟に考える方も増えています。大切なのは、相手との関係性や地域の慣習も考慮することです。私の場合も、親族と友人では少し金額を変えましたし、特にお世話になった方には気持ち多めにお返しさせていただきました。
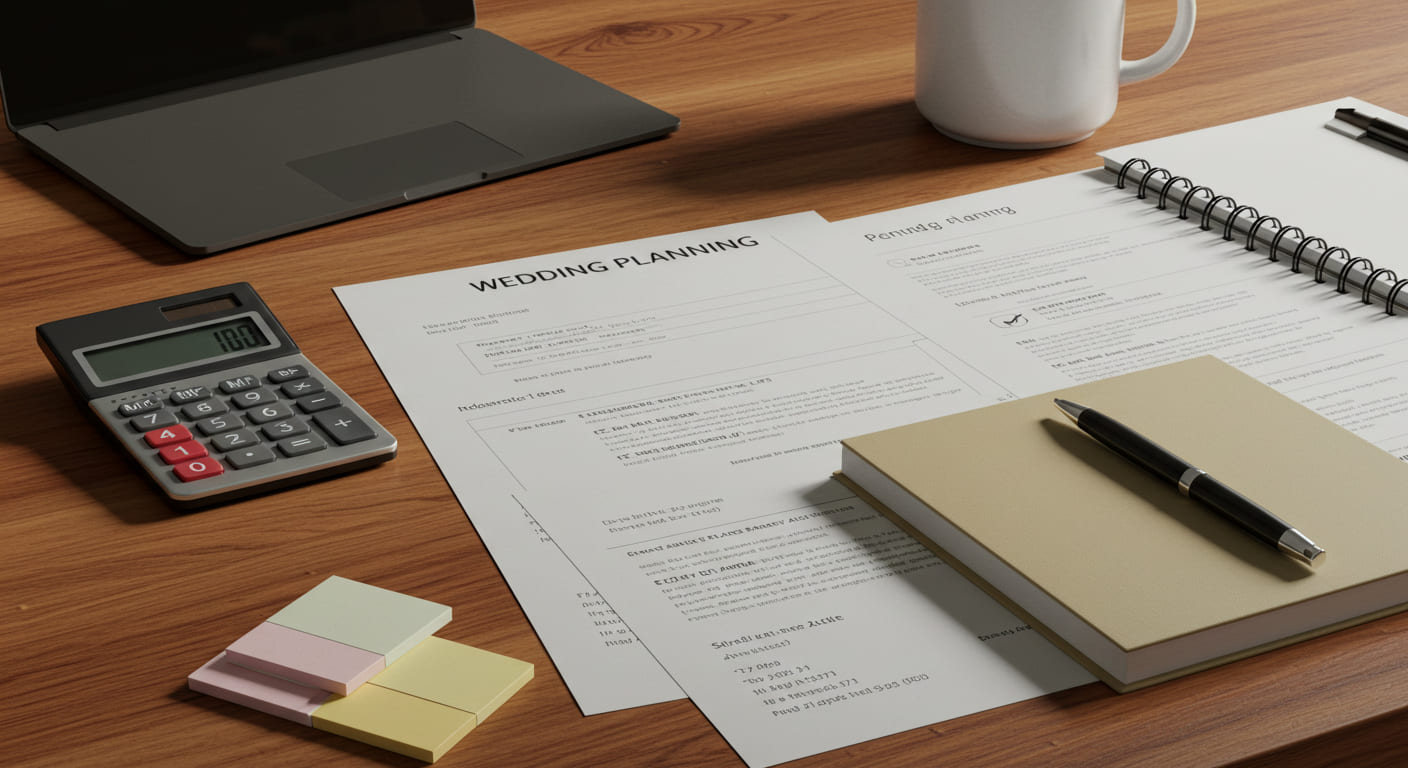
半返しの原則と例外ケース
「半返し」というのは、いただいたお祝いの半額程度をお返しするという考え方です。でも実際のところ、この「半返し」にもいろいろな解釈があるんですよね。私も最初は「きっちり半額じゃないとダメなの?」って思っていましたが、そこまで厳密ではないんです。
例えば、親や兄弟姉妹など身内からの高額なお祝いには、3分の1程度でも十分とされています。逆に、職場関係や親戚など、今後のお付き合いを考慮したい相手には、しっかり半額程度をお返しするのが無難です。
私が体験した例外ケースをいくつかご紹介すると、確か3年前の秋頃だったかな、叔父から10万円という高額なお祝いをいただいた時は、5万円分お返しするのは現実的じゃないと判断して、3万円程度の上質なギフトセットにしました。その代わり、心のこもったお礼状を添えて、感謝の気持ちをしっかり伝えるようにしたんです。
また、友人同士の連名で1万円をいただいた場合は、みんなで分けられるお菓子セットを5千円程度で用意しました。こういう時は、きっちり計算するよりも、みんなが楽しめることを優先したほうがいいんですよね。
関係性別の相場目安
関係性によって相場感をまとめてみると、以下のような目安になります。これは私が実際に調べて、周りの経験談も参考にした表です。
| 関係性 | いただく金額の目安 | 内祝いの相場 | 選ぶ商品の特徴 |
|---|---|---|---|
| 両親・兄弟姉妹 | 5万円〜10万円 | 3分の1程度 | 甘えても良い関係 |
| 親戚・親族 | 3万円〜5万円 | 半額程度 | 格式を重視 |
| 職場上司 | 1万円〜3万円 | 半額程度 | 今後の関係も考慮 |
| 友人・同僚 | 1万円〜3万円 | 半額程度 | 実用性重視 |
| 職場一同 | 5千円〜1万円 | 半額程度 | みんなで分けられるもの |
この表を参考にしつつ、最終的には相手の気持ちを考えて調整するのがベストです。金額よりも、「ちゃんと考えて選んでくれたんだな」ということが伝わることの方が大切なんですよね。
出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2024
によると、内祝いの平均額は全体的に上昇傾向にあるものの、相手への配慮を重視する傾向も強まっているそうです。やっぱり金額だけでなく、気持ちを込めることが重要視されているんですね。
のしと表書きの正しいマナー
のしの書き方って、正直言うと私も最初は全然わからなくて困りました。「結び切り?蝶結び?」「表書きは何て書くの?」「名前は旧姓?新姓?」…疑問だらけで、確か母に電話で聞きながら準備した記憶があります。
でも一度覚えてしまえば、そんなに難しくないんです。のしは相手への敬意を表す大切な要素なので、基本的なルールは押さえておきたいところですね。特に年配の方は、のしがきちんとしているかどうかをよく見ていらっしゃるので、失礼のないようにしたいものです。
そういえば、この前友人が「のしって自分で書くの?お店でやってもらうの?」って聞いてきたんですが、最近はお店で丁寧に書いてもらえるところが多いので、そんなに心配しなくても大丈夫なんですよね。

のしの基本ルールと選び方
のしで一番重要なのは「水引」の選び方です。結婚内祝いでは、必ず「結び切り」を使います。これは「一度きりの慶事」という意味で、結婚は何度も繰り返すものではないからです。間違っても「蝶結び」は使わないでくださいね。私も最初、デパートで「どちらにしますか?」って聞かれて迷ったんですが、店員さんが教えてくれました。
水引の色は、紅白または金銀が一般的です。紅白の方が一般的で、金銀は特に格式を重視したい場合に使います。本数は5本か10本ですが、結婚関連では10本が正式とされています。まあ、最近はあまり細かく気にする人も少なくなってきているようですが、基本は知っておいた方が安心ですよね。
のしの大きさも、贈り物の大きさに合わせて選びます。小さな品物に大きなのしをつけるとバランスが悪いですし、逆も然りです。お店の方に相談すれば、適切なサイズを選んでくれますよ。
表書きの書き方と注意点
表書きは「内祝」または「結婚内祝」と書くのが一般的です。私は「内祝」にしましたが、どちらでも問題ありません。「寿」と書く場合もありますが、これは結婚式の引き出物などでよく使われるので、内祝いでは「内祝」の方が適切だと思います。
下段には贈り主の名前を書きますが、ここが一番悩むところかもしれません。結婚後なら新しい姓で、夫婦連名で書くのが基本です。「田中太郎・花子」のように、右側に夫の名前、左側に妻の名前を書きます。
ただし、職場関係で旧姓の方が通りが良い場合は、カッコ内に旧姓を併記することもあります。例えば「田中花子(旧姓:佐藤)」のような感じですね。うろ覚えなんですが、確か地域によっては両家の姓を併記するところもあったような気がします。詳しくは覚えてないんですが、その辺りは地域の慣習に合わせるのが良いでしょう。
大切なのは、相手が「誰からのお返し」なのかすぐにわかることです。特に親戚関係では、姓が変わったことを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、そういった配慮も必要ですね。
KIZUNAのようなカード型ギフトサービスでも、のしのデザインはちゃんと用意されていて、名前の印字も対応してもらえます。最近はこういったサービスを利用する方も増えているので、準備の手間を省きたい場合は検討してみても良いかもしれません。
よくある質問(FAQ)
-2.jpg)
内祝いはいつまでに贈ればいい?
これは本当によく聞かれる質問です。基本的には、お祝いをいただいてから1ヶ月以内に贈るのがマナーとされています。私の場合は、お祝いをいただいた日をメモしておいて、遅くても3週間以内には発送するようにしていました。
ただし、結婚式を挙げる場合は、式後1ヶ月以内でも大丈夫です。式の準備で忙しいのは皆さんわかってくださいますからね。万が一遅れてしまった場合は、お詫びの一言を添えることが大切です。私の友人も、新婚旅行から帰ってきてから慌てて準備していましたが、丁寧なお礼状と一緒に贈ったら、皆さん快く受け取ってくださったそうです。
連名でお祝いをもらった場合は?
夫婦連名でお祝いをいただいた場合は、基本的に1つの内祝いで大丈夫です。ただし、のしには「○○様・○○様」と連名でいただいた通りに、こちらも連名でお返しするのがマナーです。
私が悩んだのは、友人カップルから連名でお祝いをいただいた時でした。まだ結婚前のカップルだったので、それぞれ個別にお返しした方がいいのか迷ったんです。結局、1つの内祝いにして、二人の名前を併記した形でお贈りしたら、とても喜んでもらえました。
商品券やギフトをもらった時の対応は?
金額がわからない商品券やギフトをいただいた時って、本当に困りますよね。私も実際に経験があります。そういう時は、同じブランドのオンラインショップで似たような商品の価格を調べてみるのが一つの方法です。
どうしてもわからない場合は、3,000円、5,000円、10,000円のどの価格帯に近いかを推測して、その半額程度で内祝いを準備します。迷った時は、少し多めに見積もった方が安全だと思います。私の経験では、心配しすぎるより、感謝の気持ちがしっかり伝わることの方が大切です。
職場の皆さんからお祝いをもらった場合は?
職場一同からお祝いをいただいた場合は、みんなで分けられるお菓子や食べ物でお礼するのが一般的です。個包装のものを人数分より少し多めに用意して、「心ばかりの品ですが」というメッセージを添えます。
私の場合は、20人程度の部署から3万円のお祝いをいただいたので、1万5千円程度の詰め合わせお菓子を選びました。のしには「御礼」と書いて、自分たちの名前を入れます。後日、「美味しかったです」という声をたくさんいただけて、本当に嬉しかったです。
結婚式を挙げない場合でも内祝いは必要?
はい、式を挙げない場合でもお祝いをいただいたら内祝いは必要です。むしろ、式がない分、お祝いをくださった方への感謝をより丁寧に表現したいものですよね。
入籍の報告をした日を起点に考えて、1ヶ月以内を目安に準備すれば良いでしょう。お礼状には「ささやかながら内祝いをお贈りします」という一文を添えると、気持ちが伝わりやすくなります。
お礼状は手書きでないとダメ?
手書きの方が気持ちは伝わりやすいですが、印刷でも全然問題ありません。大切なのは、感謝の気持ちがきちんと込められているかどうかです。私の場合は、印刷した文章の最後に手書きで一言添えるようにしていました。
この記事のまとめ
結婚内祝いについて、基本的な意味から具体的な選び方、金額設定、のしのマナーまで詳しくお話ししてきました。私自身の体験を振り返ってみると、最初は本当にわからないことだらけで不安でしたが、一つひとつ丁寧に準備していけば、きっと感謝の気持ちは相手に伝わるものだと感じています。
まず、結婚内祝いは単なる「お返し」ではなく、喜びを分かち合うという本来の意味があることを理解できました。現代では感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとしての役割が重要で、相手との関係をより良好に保つための大切な習慣なんですね。
選び方については、相手との関係性を最優先に考えることが成功の秘訣です。年齢層や親密度、ライフスタイルを考慮して、消えものか長く使えるものを中心に選べば失敗は少ないでしょう。最近人気のカタログギフトやカード型サービスなら、相手が自分で選べるので安心です。
金額設定では「半返し」が基本原則ですが、関係性によって柔軟に調整することが大切です。身内には3分の1程度、職場関係や親戚にはしっかり半額程度を目安にしつつ、何より相手のことを思って選ぶ気持ちが重要です。
のしについては、結び切りの水引を使い、表書きは「内祝」、名前は夫婦連名で書くのが基本ルール。細かいマナーも大切ですが、相手への敬意を表すという心構えがあれば大丈夫です。
私が一番お伝えしたいのは、完璧を求めすぎなくても良いということです。形式やマナーも大切ですが、それ以上に「お祝いをくださった方への感謝の気持ちを伝えたい」という思いがあれば、きっと相手にも伝わります。結婚という人生の節目に、大切な方々との関係を深めるきっかけとして、心を込めて内祝いを準備していただければと思います。





