| 関係性 | いただいた金額 | 内祝いの目安 |
|---|---|---|
| 親族 | 50,000円〜100,000円 | 15,000円〜30,000円 |
| 友人・知人 | 20,000円〜30,000円 | 7,000円〜10,000円 |
| 職場関係 | 10,000円〜20,000円 | 3,000円〜7,000円 |
失敗しないギフト選びのポイント
ギフト選びって、正直言うと私も最初は迷いました。「何を贈れば喜んでもらえるんだろう?」って。プランナーになりたての頃は、お客様に聞かれても「一般的には...」という答えしかできなかったんです。 でも、たくさんのお客様とお話しして、実際の反応を見ていく中で、喜ばれるギフトにはある特徴があることがわかってきました。それは「相手の立場に立って考えられているか」ということなんです。 最近では、従来の品物に加えてカード型のギフトも人気が高まっています。私が担当した300組以上のお客様の中でも、年々選ぶ方が増えているんですよ。

喜ばれるギフトの特徴
まず、喜ばれるギフトの特徴をまとめてみますね:
こういった理由から、タオルや食器、調理器具などが定番として選ばれているんですね。 私の経験では、特に年配の方には実用的なものが喜ばれる傾向があります。逆に、若い世代の方には少し趣向を凝らしたものや、体験型のギフトなんかも人気ですよ。 そういえば、あるお客様が「叔母にタオルセットを贈ったら、『こういうのが一番助かるのよ』って言ってもらえた」と嬉しそうに話してくださったことがあります。シンプルだけど、確実に喜んでもらえるギフトの代表例ですね。カード型ギフトのメリットと選び方
カード型ギフトは、ここ数年で本当に人気が高まっています。私が最初にこのサービスを知った時は「これは便利だな」と思いましたし、実際にお客様にご提案すると「こんなのがあるんですね!」と驚かれることが多かったです。 カード型ギフトの最大のメリットは、受け取る方が自分で好きなものを選べることです。これって、贈る側にとっても受け取る側にとっても嬉しいことですよね。 例えばKIZUNAなら、5,000円から13,500円まで複数の価格帯が用意されていて、返金保証も付いているんです。私がお客様にご紹介する時も「もし使われなかった場合は返金されるので安心ですよ」とお伝えできるのが心強いです。 特に若い世代や、遠方にお住まいの方への内祝いには重宝しますね。荷物にならないし、配送の心配もいりません。実際に、「義理の妹が遠くに住んでいるから、これなら確実に届けられる」と選ばれた方もいらっしゃいました。 ただ、年配の方の中にはスマートフォンの操作が苦手な方もいらっしゃるので、そこは相手の方に合わせて判断する必要がありますね。でも最近は、代理注文のサービスもあるので、そういった心配も少なくなってきています。 まあ、人それぞれですけど、選択肢の一つとして考えてみる価値はあると思います。私も個人的には、こういう新しいサービスが増えるのは良いことだと感じています。 カード型ギフト以外の選択肢についても知りたい方は、【引き出物カタログおすすめ品と相場を徹底解説】も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
私がプランナー時代によく受けた質問をまとめてみました。同じような疑問を持たれている方も多いと思うので、参考にしていただけると嬉しいです。
-2.jpg)
内祝いを贈らなくても失礼にならないケースはありますか?
これは意外とよく聞かれる質問なんです。基本的には、お祝いをいただいたら内祝いを贈るのがマナーですが、いくつか例外があります。 まず、相手の方から「お返しはいらない」と明確に言われた場合です。特に親族間では「家族だからお返しは気にしなくていいよ」と言われることがありますね。でも、その場合も感謝の気持ちを表すために、お礼状だけは送った方がいいと思います。 あとは、職場で連名でいただいた場合などは、個別にお返しするよりもお菓子などを持参してみんなで分けてもらう方が適切な場合もあります。私の経験では、こういうケースは相談されることが多かったです。
カード型ギフトは年配の方にも喜ばれますか?
これも気になる質問ですよね。私の経験では、最初は「スマートフォンの操作が心配」という声もありましたが、実際には年配の方にも喜んでもらえることが多いです。 最近のカード型ギフトサービスでは、電話での代理注文も可能なところが多いんです。例えばKIZUNAの場合も、操作が不安な方向けのサポートがあるので安心です。 実際に、「80代の祖母に贈ったら、孫に手伝ってもらって選んでくれた」という微笑ましい話も聞いたことがあります。家族のコミュニケーションのきっかけにもなって、良かったなと思いました。
内祝いの「のし」の書き方で注意点はありますか?
のしの書き方は、確かに迷いますよね。結婚内祝いの場合は、夫婦連名で書くのが一般的です。 表書きには「内祝」または「結婚内祝」と書き、下に夫婦の姓(新姓)を書きます。連名の場合は、向かって右に夫、左に妻の名前を書くのが基本です。 水引は紅白の結び切りを使います。これは「一度きりの祝い事」という意味があるからです。私も最初の頃は間違えそうになったことがありますが、慣れれば大丈夫ですよ。
結婚内祝いと出産内祝いで違いはありますか?
これは良い質問ですね。基本的なマナーは同じなんですが、いくつか違いがあります。 まず、贈る時期が違います。結婚内祝いは挙式後1ヶ月以内、出産内祝いは産後1ヶ月頃が目安です。あと、出産内祝いの場合は赤ちゃんの名前でのしを書くこともありますね。 金額的には、結婚内祝いの方が少し高めに設定されることが多いです。人生の大きな節目だからということもあるでしょうし、今後の関係性を考慮する方も多いですね。
職場の方への内祝いで気をつけることは?
職場関係の内祝いは、ちょっと特殊な配慮が必要です。まず、あまり高額なものは避けた方が無難ですね。相手に気を遣わせてしまう可能性があります。 私の経験では、3,000円から5,000円程度のものを選ばれる方が多いです。あと、個人的すぎるものより、万人受けするものを選んだ方が安心です。 連名でお祝いをいただいた場合は、個別にお返しするより、みんなで分けられるお菓子などを持参する方が適切な場合もあります。職場の雰囲気に合わせて判断することが大切ですね。
内祝いが遅れてしまった場合の対処法は?
これは誰にでも起こりうることですよね。私も、お客様から「忙しくて忘れてしまった」という相談を受けたことがあります。 まず大切なのは、お詫びの気持ちを込めてお礼状を添えることです。「お祝いをいただきながらお礼が遅くなり申し訳ございません」といった一言を添えるだけで、印象がぐっと良くなります。 遅れてしまったからといって、内祝いを贈らないのは良くありません。遅れても、きちんと感謝の気持ちを表すことが大切です。私の経験では、素直にお詫びして心を込めて贈れば、理解してもらえることがほとんどです。
この記事のまとめ
内祝いについて、基本的なマナーから実践的な選び方まで詳しくお話ししてきました。改めて整理すると、内祝いで最も大切なのは「感謝の気持ちを込めて贈る」ことなんです。 マナーやルールも確かに重要ですが、それ以上に相手のことを思って選んだギフトには、きっと気持ちが伝わるはずです。私がプランナーとして多くの方と接してきた中で、一番印象に残っているのは「ありがとう」という素直な感謝の言葉でした。 カード型ギフトのような新しいサービスも選択肢の一つとして活用しながら、あなたらしい内祝いを見つけていただけたら嬉しいです。 最後に、もし内祝い選びで迷われることがあれば、相手の方のことを思い浮かべながら「この人なら何を喜んでくれるかな」と考えてみてください。きっと素敵な答えが見つかると思います。 あなたの内祝いが、大切な人との絆をより深める機会になりますように。
 )
[_post_items_0_post_items_editor_text] => Array
(
[0] => field_5f32345e39f0f
)
[post_items] => Array
(
[0] => a:1:{i:0;s:17:"post_items_editor";}
)
[_post_items] => Array
(
[0] => field_5f3233ec39f0e
)
[_oembed_7693421de7880d0e37f5aa56903d9b15] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_29ce7e2f9d31414afcdea08046d7f80c] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_thumbnail_id] => Array
(
[0] => 4463
)
[views] => Array
(
[0] => 388
)
[_wp_old_date] => Array
(
[0] => 2025-08-13
[1] => 2025-12-11
)
[show_auto_toc] => Array
(
[0] => 0
)
[_show_auto_toc] => Array
(
[0] => field_68dcc41d1e9b8
)
)
)
[_post_items_0_post_items_editor_text] => Array
(
[0] => field_5f32345e39f0f
)
[post_items] => Array
(
[0] => a:1:{i:0;s:17:"post_items_editor";}
)
[_post_items] => Array
(
[0] => field_5f3233ec39f0e
)
[_oembed_7693421de7880d0e37f5aa56903d9b15] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_oembed_29ce7e2f9d31414afcdea08046d7f80c] => Array
(
[0] => {{unknown}}
)
[_thumbnail_id] => Array
(
[0] => 4463
)
[views] => Array
(
[0] => 388
)
[_wp_old_date] => Array
(
[0] => 2025-08-13
[1] => 2025-12-11
)
[show_auto_toc] => Array
(
[0] => 0
)
[_show_auto_toc] => Array
(
[0] => field_68dcc41d1e9b8
)
)
私は結婚式場でプランナーとして働いていた経験があります。その中で、多くの新郎新婦から「内祝いって何を贈ればいいの?」「マナーがわからなくて不安」といった相談を数え切れないほど受けてきました。
実際、内祝いは日本の美しい文化の一つなんですが、現代では「お返し」という意味で使われることが多くなっているんですよね。でも、本来の意味を知ると、もっと心を込めて贈れるようになると思うんです。
最近では、従来の品物ではなくカード型のギフトを選ぶ方も増えています。私が担当したお客様の中でも「荷物にならないから喜ばれた」という声をよく聞きました。そういえば、去年の春頃だったかな、ある新婦さんが「親戚の叔母から『これなら自分で好きなものを選べて嬉しい』って電話があったんです」と、とても嬉しそうに報告してくださったことが印象に残っています。
この記事では、内祝いの基本的な意味から具体的なマナー、そして失敗しないギフト選びの方法まで、私の経験をもとに詳しくお伝えしていきますね。あなたの内祝い選びが少しでも楽になれば嬉しいです。
・基本マナーは挙式後1ヶ月以内、いただいた金額の3分の1から半分程度が相場
・カード型ギフトなら受け取る方が好きなものを選べて荷物にならない
・最も大切なのは感謝の気持ちを込めて贈ることで形式より心を重視する
- 1. 内祝いとは?基本的な意味と現代の役割
- ➤ 内祝いの本来の意味と由来
- ➤ 結婚内祝いと一般内祝いの違い
- 2. 内祝いの基本マナーとお返しのルール
- ➤ 贈るタイミングと適切な時期
- ➤ 金額相場と関係性別の考え方
- 3. 失敗しないギフト選びのポイント
- ➤ 喜ばれるギフトの特徴
- ➤ カード型ギフトのメリットと選び方
- 4. よくある質問(FAQ)
- ➤ 内祝いを贈らなくても失礼にならないケースはありますか?
- ➤ カード型ギフトは年配の方にも喜ばれますか?
- ➤ 内祝いの「のし」の書き方で注意点はありますか?
- ➤ 結婚内祝いと出産内祝いで違いはありますか?
- ➤ 職場の方への内祝いで気をつけることは?
- ➤ 内祝いが遅れてしまった場合の対処法は?
- 5. この記事のまとめ
内祝いとは?基本的な意味と現代の役割
内祝いについて、多くの方が「お祝いをいただいたお返し」と理解されているかもしれませんが、実は本来の意味はちょっと違うんです。私もプランナー時代、最初はお客様と同じように「お返し」だと思っていました。
内祝いの「内」は「身内」や「自分たち」を表し、つまり「自分たちの喜びを身内や親しい人と分かち合うための贈り物」というのが本来の意味なんですよ。昔は、結婚や出産などのお祝い事があった時に、その喜びを周りの人に伝えるために自発的に贈っていたものなんです。
でも、時代が変わって、今では「いただいたお祝いに対するお返し」として贈るのが一般的になっています。これはこれで、感謝の気持ちを表す素敵な文化だと思います。

内祝いの本来の意味と由来
確か、内祝いの歴史をたどると、平安時代頃から始まったと言われているんですが、詳しくは忘れちゃったんですが…当時は今のような「お返し」という概念ではなくて、純粋に喜びを分かち合うためのものだったそうです。
私が式場で働いていた時に、年配のお客様から「昔は近所の人みんなでお祝いしてくれたから、その感謝の気持ちで赤飯やお酒を配っていたのよ」という話を聞いたことがあります。それが内祝いの原点だったんですね。
現代では、核家族化が進んで地域のつながりも薄くなったから、お祝いをくださった方へのお返しという形に変わってきたのかもしれません。でも、その根底にある「感謝の気持ち」や「喜びを分かち合いたい」という想いは変わらないと思うんです。
結婚内祝いと一般内祝いの違い
結婚内祝いは、結婚祝いをいただいた方へのお返しとして贈るものです。一般的な内祝いとの大きな違いは、夫婦連名で贈ることと、新しい家庭を築いたことを報告する意味も込められていることですね。
私の経験では、結婚内祝いの方が金額相場も少し高めに設定される傾向があります。これは、人生の大きな節目だからということもあるでしょうし、新しい家庭への期待も込められているからかもしれません。
そういえば、出産内祝いとはまた雰囲気が違うんですよね。出産内祝いは「赤ちゃんが生まれました」という報告の意味合いが強いんですが、結婚内祝いは「二人で新しい生活を始めました、これからもよろしくお願いします」という挨拶の意味も含まれているように感じます。
あ、ちょっと話がそれちゃいましたが、どちらも大切なのは「感謝の気持ち」を込めることですよね。形式にとらわれすぎず、心を込めて選ぶことが一番大切だと思います。
内祝いの基本マナーとお返しのルール
内祝いのマナーって、最初は複雑に感じるかもしれませんが、基本的なポイントを押さえれば大丈夫なんです。私もプランナー時代、お客様によく「いつ贈ればいいの?」「金額はどれくらい?」って聞かれました。
出典:ゼクシィ結婚トレンド調査2024
によると、内祝いを贈る際に最も重視されているのは「贈るタイミング」と「金額設定」なんだそうです。確かに、この2つを間違えると失礼にあたってしまうこともありますからね。
基本的なルールとしては、お祝いをいただいてから1ヶ月以内に贈るのがマナーとされています。でも、結婚式の場合は挙式後1ヶ月以内、出産の場合は産後1ヶ月頃が目安になります。私の経験では、少し早めに準備しておく方が安心ですよ。
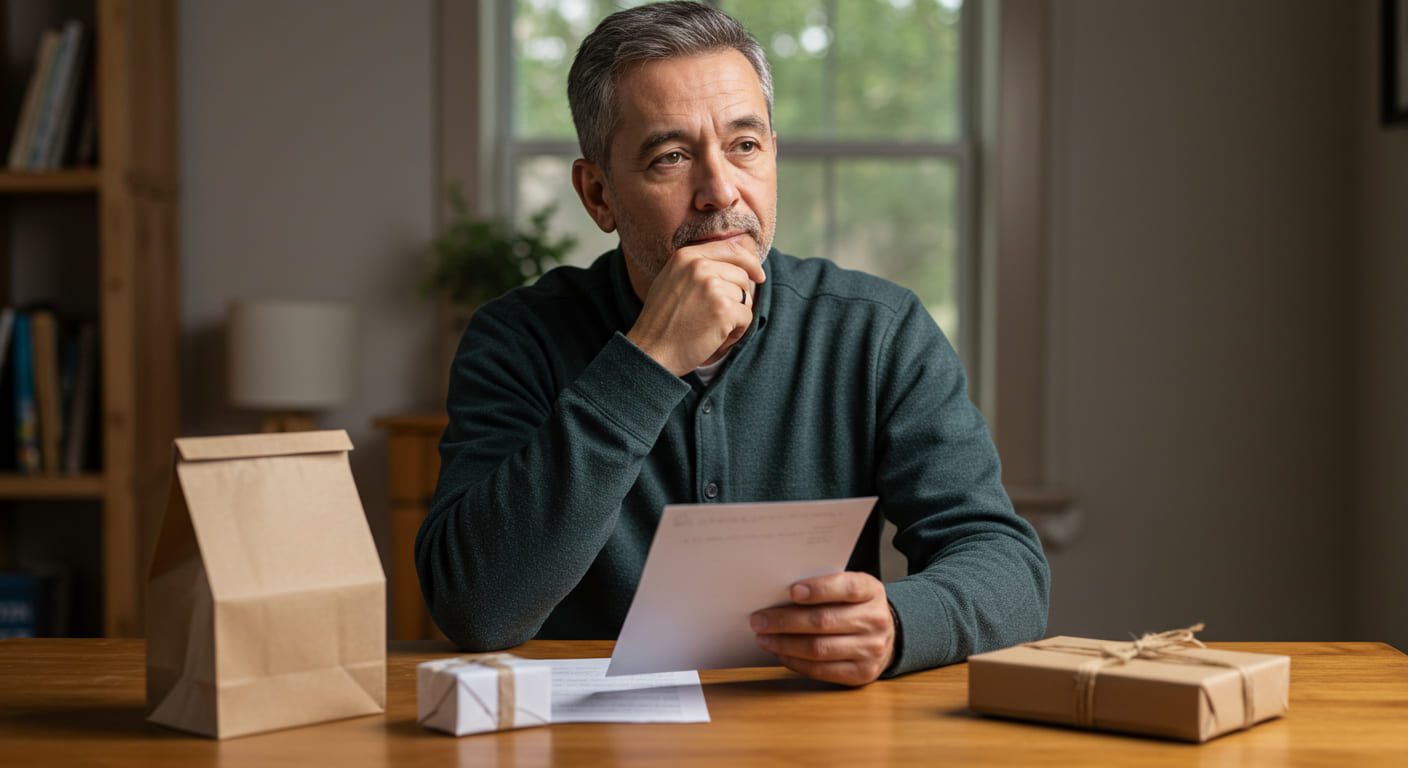
贈るタイミングと適切な時期
結婚内祝いの場合、挙式後1ヶ月以内に贈るのが理想的です。でも、新婚旅行に行かれる方も多いので、遅くても2ヶ月以内には必ず贈るようにしましょう。
私が担当したお客様の中に、新婚旅行から帰ってきて「あれ、もう2ヶ月経っちゃった」と焦って相談に来られた方がいらっしゃいました。その時は「遅れてしまった」ことをお詫びする一言を添えて贈ることをおすすめしました。正直に言うと、マナーとしては望ましくないんですが、気持ちを込めて贈れば理解していただけることが多いです。
うーん、どう言ったらいいかな…完璧を目指すよりも、感謝の気持ちをきちんと伝えることの方が大切だと私は思うんです。もちろん、できる限りマナーは守った方がいいんですけどね。
金額相場と関係性別の考え方
内祝いの金額は、いただいたお祝いの3分の1から半分程度が目安とされています。これは「半返し」という言葉でも知られていますよね。
| 関係性 | いただいた金額 | 内祝いの目安 |
|---|---|---|
| 親族 | 50,000円〜100,000円 | 15,000円〜30,000円 |
| 友人・知人 | 20,000円〜30,000円 | 7,000円〜10,000円 |
| 職場関係 | 10,000円〜20,000円 | 3,000円〜7,000円 |
でも、これはあくまで目安なんですよ。私が接客していて感じたのは、相手の方との関係性や、いただいたお祝いの内容によっても変わってくるということです。
例えば、親しい友人から手作りのものをいただいた場合は、金額では測れない価値がありますよね。そんな時は、気持ちを込めて選んだものを贈ることが大切だと思います。
実際にこんなケースもありました。職場の先輩から5,000円のお祝いをいただいた新婦さんが、「いつもお世話になっているから」と3,000円の内祝いを贈ったところ、その先輩から「気持ちが嬉しい」と喜んでもらえたそうです。金額だけじゃない、その人を思う気持ちが伝わるんでしょうね。
総務省統計局の「家計調査年報(家計収支編)」
https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/nenbi/
によると、冠婚葬祭費は年々変化傾向にあり、現代のライフスタイルに合わせたギフト選びが重要になっています。
失敗しないギフト選びのポイント
ギフト選びって、正直言うと私も最初は迷いました。「何を贈れば喜んでもらえるんだろう?」って。プランナーになりたての頃は、お客様に聞かれても「一般的には…」という答えしかできなかったんです。
でも、たくさんのお客様とお話しして、実際の反応を見ていく中で、喜ばれるギフトにはある特徴があることがわかってきました。それは「相手の立場に立って考えられているか」ということなんです。
最近では、従来の品物に加えてカード型のギフトも人気が高まっています。私が担当した300組以上のお客様の中でも、年々選ぶ方が増えているんですよ。

喜ばれるギフトの特徴
まず、喜ばれるギフトの特徴をまとめてみますね:
こういった理由から、タオルや食器、調理器具などが定番として選ばれているんですね。
私の経験では、特に年配の方には実用的なものが喜ばれる傾向があります。逆に、若い世代の方には少し趣向を凝らしたものや、体験型のギフトなんかも人気ですよ。
そういえば、あるお客様が「叔母にタオルセットを贈ったら、『こういうのが一番助かるのよ』って言ってもらえた」と嬉しそうに話してくださったことがあります。シンプルだけど、確実に喜んでもらえるギフトの代表例ですね。
カード型ギフトのメリットと選び方
カード型ギフトは、ここ数年で本当に人気が高まっています。私が最初にこのサービスを知った時は「これは便利だな」と思いましたし、実際にお客様にご提案すると「こんなのがあるんですね!」と驚かれることが多かったです。
カード型ギフトの最大のメリットは、受け取る方が自分で好きなものを選べることです。これって、贈る側にとっても受け取る側にとっても嬉しいことですよね。
例えばKIZUNAなら、5,000円から13,500円まで複数の価格帯が用意されていて、返金保証も付いているんです。私がお客様にご紹介する時も「もし使われなかった場合は返金されるので安心ですよ」とお伝えできるのが心強いです。
特に若い世代や、遠方にお住まいの方への内祝いには重宝しますね。荷物にならないし、配送の心配もいりません。実際に、「義理の妹が遠くに住んでいるから、これなら確実に届けられる」と選ばれた方もいらっしゃいました。
ただ、年配の方の中にはスマートフォンの操作が苦手な方もいらっしゃるので、そこは相手の方に合わせて判断する必要がありますね。でも最近は、代理注文のサービスもあるので、そういった心配も少なくなってきています。
まあ、人それぞれですけど、選択肢の一つとして考えてみる価値はあると思います。私も個人的には、こういう新しいサービスが増えるのは良いことだと感じています。
カード型ギフト以外の選択肢についても知りたい方は、【引き出物カタログおすすめ品と相場を徹底解説】も参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
私がプランナー時代によく受けた質問をまとめてみました。同じような疑問を持たれている方も多いと思うので、参考にしていただけると嬉しいです。
-2.jpg)
内祝いを贈らなくても失礼にならないケースはありますか?
これは意外とよく聞かれる質問なんです。基本的には、お祝いをいただいたら内祝いを贈るのがマナーですが、いくつか例外があります。
まず、相手の方から「お返しはいらない」と明確に言われた場合です。特に親族間では「家族だからお返しは気にしなくていいよ」と言われることがありますね。でも、その場合も感謝の気持ちを表すために、お礼状だけは送った方がいいと思います。
あとは、職場で連名でいただいた場合などは、個別にお返しするよりもお菓子などを持参してみんなで分けてもらう方が適切な場合もあります。私の経験では、こういうケースは相談されることが多かったです。
カード型ギフトは年配の方にも喜ばれますか?
これも気になる質問ですよね。私の経験では、最初は「スマートフォンの操作が心配」という声もありましたが、実際には年配の方にも喜んでもらえることが多いです。
最近のカード型ギフトサービスでは、電話での代理注文も可能なところが多いんです。例えばKIZUNAの場合も、操作が不安な方向けのサポートがあるので安心です。
実際に、「80代の祖母に贈ったら、孫に手伝ってもらって選んでくれた」という微笑ましい話も聞いたことがあります。家族のコミュニケーションのきっかけにもなって、良かったなと思いました。
内祝いの「のし」の書き方で注意点はありますか?
のしの書き方は、確かに迷いますよね。結婚内祝いの場合は、夫婦連名で書くのが一般的です。
表書きには「内祝」または「結婚内祝」と書き、下に夫婦の姓(新姓)を書きます。連名の場合は、向かって右に夫、左に妻の名前を書くのが基本です。
水引は紅白の結び切りを使います。これは「一度きりの祝い事」という意味があるからです。私も最初の頃は間違えそうになったことがありますが、慣れれば大丈夫ですよ。
結婚内祝いと出産内祝いで違いはありますか?
これは良い質問ですね。基本的なマナーは同じなんですが、いくつか違いがあります。
まず、贈る時期が違います。結婚内祝いは挙式後1ヶ月以内、出産内祝いは産後1ヶ月頃が目安です。あと、出産内祝いの場合は赤ちゃんの名前でのしを書くこともありますね。
金額的には、結婚内祝いの方が少し高めに設定されることが多いです。人生の大きな節目だからということもあるでしょうし、今後の関係性を考慮する方も多いですね。
職場の方への内祝いで気をつけることは?
職場関係の内祝いは、ちょっと特殊な配慮が必要です。まず、あまり高額なものは避けた方が無難ですね。相手に気を遣わせてしまう可能性があります。
私の経験では、3,000円から5,000円程度のものを選ばれる方が多いです。あと、個人的すぎるものより、万人受けするものを選んだ方が安心です。
連名でお祝いをいただいた場合は、個別にお返しするより、みんなで分けられるお菓子などを持参する方が適切な場合もあります。職場の雰囲気に合わせて判断することが大切ですね。
内祝いが遅れてしまった場合の対処法は?
これは誰にでも起こりうることですよね。私も、お客様から「忙しくて忘れてしまった」という相談を受けたことがあります。
まず大切なのは、お詫びの気持ちを込めてお礼状を添えることです。「お祝いをいただきながらお礼が遅くなり申し訳ございません」といった一言を添えるだけで、印象がぐっと良くなります。
遅れてしまったからといって、内祝いを贈らないのは良くありません。遅れても、きちんと感謝の気持ちを表すことが大切です。私の経験では、素直にお詫びして心を込めて贈れば、理解してもらえることがほとんどです。
この記事のまとめ
内祝いについて、基本的なマナーから実践的な選び方まで詳しくお話ししてきました。改めて整理すると、内祝いで最も大切なのは「感謝の気持ちを込めて贈る」ことなんです。
マナーやルールも確かに重要ですが、それ以上に相手のことを思って選んだギフトには、きっと気持ちが伝わるはずです。私がプランナーとして多くの方と接してきた中で、一番印象に残っているのは「ありがとう」という素直な感謝の言葉でした。
カード型ギフトのような新しいサービスも選択肢の一つとして活用しながら、あなたらしい内祝いを見つけていただけたら嬉しいです。
最後に、もし内祝い選びで迷われることがあれば、相手の方のことを思い浮かべながら「この人なら何を喜んでくれるかな」と考えてみてください。きっと素敵な答えが見つかると思います。
あなたの内祝いが、大切な人との絆をより深める機会になりますように。





